8.2012年9月11日(火)
パリ(オルセー美術館)、パリ発 フランクフルト乗り継ぎ
起床(0500)朝食(0630)オルセー美術館(0925~1200)空港着(1413))搭乗(1643)<エールフランス AF2318便 24BC>離陸(1720)軽食(1735)着陸(1815)ラウンジ(1933~2010)搭乗(2045)<JL0408便 47BC>離陸(2119)食事(2245・・日本時間 +7時間 =0545)
8-1 朝
起床(0500)朝食(0630)
今日は最後の朝だったが、久しぶりに目覚ましで起きた。そう長い旅行でもないし、昨日そんなに深酒したわけでもないし、やはり年齢には勝てないのかとも思う。自分の体力ともう少し相談して行動すべきかも知れないと反省。
荷作りを完了してから、昨日印刷した絵葉書を書いたりした。
それから朝食に行った。ここは中国系のホテルということで、中国系の人も多かった。レストランにも中華料理っぽいものがあったりした。
が、我々の食べたのは、いつものメニューになってしまった。添乗員さんの横に座ったので、少し話をした。今回に限らず、あまり添乗員さんと話すチャンスもないので、面白かった。
出発が午後なので、それまで自由時間になった。どうしようかと思ったが、添乗員さんが希望者だけオルセー美術館に連れて行ってくれるというので、それに乗ることにした。
そのために、チェックアウトを先に済ませて、スーツケース等の荷物は、ホテルへ預けた。
8-2 初めての地下鉄
ホテル発(0835)
出発する頃になるとぽつぽつと小雨が降り出した。
地下鉄の駅はすぐ傍にあるので、濡れないように壁にへばりつくようにしながら行った。
自動販売機でまず切符を購入した。英語表記もあるので、それを見ながらということだが、後ろに長い列が出来てしまったので、添乗員さんがパッパとやってくれたので、次回できるかどうかはやや不安。それにしても、通勤時間だと思うのだが、何故にこんなに切符を買う人が多いのだろうと不思議に思った。スイカのような便利なものはないのだろうか。
切符で自動改札を通る。手前に入れると改札が開くという仕組みはお馴染みだが、その開くところが人の高さくらいあり、もそもそしているとすぐに閉まってしまうので、始めに入ろうとしたnoriは、要領が分からず顔をぶつけてしまった。junは手で押し開けた。
電車は向かい合って4人座るタイプの椅子が両側にあるので、通路が狭く、それほどの人はいないのに混み合っていた。
ドアは、手動式。うっかりしていると下りられない。
でも、ドアの上にある経路表がしっかりとしていて、しかも電光で表示してくれるので非常にわかりやすい(これは新型で、そうでないものも多くあるらしい←最後の写真がそれ、乗り継いだ電車のもの)。過ぎた駅の電光は消えるので、あといくつ、と数えながら安心して乗っていることが出来る。
また、停車した駅の駅名表示もとても大きくてわかりやすかった。
途中1回乗り換えて、約30分で目的地に着いた。乗換もまぁついていったと言えばついて行ったわけだけれど、表示はしっかりしていた。お上りさんの沢山抱えている都市だろうから、まぁ少なくともフランス語ではしっかり書いてある。ホームの出口を示す看板にも、オルセーはこっちと書いてあった(たぶん)。
8-3 オルセー美術館(0925~1200)
駅からオルセーへ行く途中にポストがあったので、朝書いた絵葉書、最後の2枚をここで出した。我々は、訪れた国の特に世界遺産を背景にした写真を自宅に送ると言うことを常にしているが、ちなみに、今回の旅行で投函した最初の頃の絵葉書は、帰宅時に既に自宅に届いていた。フランスでは郵便ポストもあちこちに見ることができて、郵便というものが制度としてきちんとあることが分かった。
目的のオルセー美術館であるが、パリ万博の時に作られた駅舎を転用した建物で、つい最近改装されたという。まぁ我々は、地下鉄の駅からパリ万博時代の駅に向かったというわけだ。
9時半に開くと言うことだったので、それに間に合うように出てきたので、丁度良い時間に着いた。でも既に沢山の既に行列が出来ていた。(この日はルーブル休館日だから特にそうだったのかも知れない。)
雨は傘を差さないで済む程度だったので、周りを見ながらしばらく待っていた。
ようやく中には入れることになったのだが、一人一人荷物つチェックがされる。これで時間がかかっていたらしい。
内部の撮影は出来ないのだが、・カメラの持ち込みは出来る。クロークに預けるのも面倒なので、誤解されないようにと身体の後ろに回して持つようにした。
入場券は、ゴッホの自画像と、駅当時から付いていた大時計の図柄。いい物が当たった。
日本語の音声ガイドを借りることにしたのだが、保証としてパスポートを預けさせられた。
そこまで添乗員さんが世話してくれた。
地図をもらっていよいよ見学だ。エスカレーターで、5階へ行く。
8-3-1 5階「印象派のギャラリー」
![761px-%C3%89douard_Manet_-_Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe[1].jpg](_src/sc4447/761px-25C32589douard_Manet_-_Le_D25C325A9jeuner_sur_l2527herbe5B15D.jpg) ○ルノワール、モネ、セザンヌなど、1860年代から1900年代にかけてのオルセー自慢の印象派コレクションが一堂に会するこのギャラリーの鑑賞は、「印象派の父」と称されるマネによる、記念碑的作品《草上の昼食》から始まる。以下は、日本語の解説の音声を頼りとした説明を中心に記載する。
○ルノワール、モネ、セザンヌなど、1860年代から1900年代にかけてのオルセー自慢の印象派コレクションが一堂に会するこのギャラリーの鑑賞は、「印象派の父」と称されるマネによる、記念碑的作品《草上の昼食》から始まる。以下は、日本語の解説の音声を頼りとした説明を中心に記載する。
この作品は劇的なスキャンダルを巻き起こした。この絵は非難され、嘲笑を受けた。マネ自身は、最初は「水浴」という題が付いていたこの作品が、批評家の気に触るとは全く考えていなかった。女性の裸体をイタリアのルネッサンス様式で描いたことで、大変気に入られるだろうと信じていた。前面に配置された3人の人物像は、ラファエルのエッチングにある「神々とニンフの像」からヒントを得て考案された。マネの絵が神話的背景を舞台にして描かれていたと簡約や批評家が知っていれば、これほどのショックを受けることはなかっただろう。
しかし、この絵の裸体の女性は、明らかにニンフではない。彼女は実在の女性だった。地面の上に脱ぎ捨てられた彼女の衣服が、彼女は普段から裸で過ごしている神話的存在などではないこと、彼女が明らかに彼女の目の前にいる男性の前で衣服を脱いだことを表している。2人の紳士は、モーニングを身につけていて、まごうことなく現代の男性達だ。彼らも実在の人物だ。絵の中で、彼女は、彼らの前で裸でいることにいささかの恥じらいも抱いていない。それどころか、彼女は画家の目を正面から見据えている。こうしたことを不適切と感じた批評家は、この絵に憤慨した。マネは、遠近法の規則を無視していること、特に奥の女性の人物を不自然に大きく描いたと言うことが、軽蔑を込めた批判を受けた。この絵の明暗のコントラストは、とてもくっきりしている。マネは、光と影の部分を案配しながら前面の若い女性に見るものの注意を引きつけている。彼女の白い肌は、2人の男性の黒いスーツに映えてひときわ浮き上がって見える。マネはまた、ここで彼の静物画家としての力量を十分に発揮しようとしている。果物、パン、そして地面の上に散らばった服の描き方には、マネがこの絵で生きる喜びを表現しようとしたことがはっきりと見える。しかし、マネの努力も徒労だった。批評家は、この絵の強いコントラストにショックを受けたばかりで、結局そこにキャンバスに乗った絵の具以上のものを見ようとしなかったということだ。
画家の批評に対し、モネは高い評価をし、彼は数年後に同じテーマで作品を制作する。この時に仕上げを除いて屋外で制作されたことが、印象派=屋外制作の発端になったとも言われている。
なお以下同様だが、特記しない限り、絵画画像の出展はWikipediaから。
![Claude_Monet_037[1].jpg](_src/sc4449/Claude_Monet_0375B15D.jpg) ○モネ「芥子の花畑」。ケシの畑に二組の親子が登場している。「ひなげし」という日本題も見られる。
○モネ「芥子の花畑」。ケシの畑に二組の親子が登場している。「ひなげし」という日本題も見られる。
クロード・モネ「芥子の花畑」は、1874年の第一回印象派展で初公開された。この絵は、単なる絵というよりも、印象派の歴史の上で最も意味ある事件の一つだ。踊るような筆の跡は、非常に素早く制作された絵のような印象を与える。モネの目的は、スナップショットのような瞬間を捕らえた絵を描くことだった。印象派の画家たちは、戸外で常に変わる光の中に身を置いて、生きた事物の世界をそのまま絵にしようとした。こうした野心を分かち持っていたモネは、瞬間のイメージを実現するために、やや神経質で、急いだタッチの画法を選んだ。そのため、この絵の中の人物像は、まるで荒いデッサンのまま残され、風景の中に半分溶け込んでしまったように見える。なぜなら、この絵の真の主題は風景だからである。当時のアカデミックな画壇の認識では、風景画はマイナーなジャンルに過ぎなかった。モネはそうした意見に与せず、自然の中に見つかる美しさのみを重んじて、自分の絵画の中心主題とした。モネがこの絵で一番描こうとしたものは、暑い夏の日の感覚であり、登場する二組の母親と子供達は、副次的なディティールにすぎない。一方母親と子供達が描き込まれていることで、田園の散歩が、19世紀に流行していた余暇であったことがわかる。19世紀前半のフランスでは、鉄道網が発達したが、そのことは都会から来る散策者に田舎の風景を益々愛好させることにつながった。この作品は、見る者が描かれた4人の人々と共に田舎を散策して風景を楽しむことが出来る絵となっている。
![737px-Berthe_Morisot_Ca%C3%A7a_de_borboleta[1].jpg](_src/sc4451/737px-Berthe_Morisot_Ca25C325A7a_de_borboleta5B15D.jpg) ○ベルト・モリゾ「蝶がり」。日本では「蝶々取り」とも。
○ベルト・モリゾ「蝶がり」。日本では「蝶々取り」とも。
ベルト・モリゾはカミーユ・コローに絵画を学んだ。日本語版Wikipediaでは、『男性中心の19世紀における女性画家ということもあって、フェミニズム研究でのアプローチが多い。』とも書かれている。実際、第1回印象派展で作品を出品した唯一の女性画家でもあった。またエドワール・マネが、彼女をモデルにした肖像画を多く描いたことでも知られる。
ベルトは最初コローの影響を受け、暗いトーンで描かれていたが、その後印象派の画家たちと付き合うようになるにつれ、ベルトのパレットは次第に明るくなっていった。1874年の第一回印象派展ではベルトの作品も並べられた。過ぎ去る感覚を何とか捕らえようとする欲求は、ベルト自身の願いでもあった。
この作品は、第一回印象派展と同じ1874年に制作された。ベルトが所属していたブルジョア階級の余暇と関連した主題であり、捕虫網で超を捕まえるという行為は、おそらく当時の有産階級に生まれ育った誰もがよく知っていた楽しみだったに違いない。
![Degas_l%27orchestre[1].jpg](_src/sc4453/Degas_l2527orchestre5B15D.jpg) ○ドガ「オペラ座のオーケストラ」。舞台のスターではなくオーケストラピットの中を描いている。
○ドガ「オペラ座のオーケストラ」。舞台のスターではなくオーケストラピットの中を描いている。
ドガは熱心なオペラファンだった。どのくらいのファンかと言えば、オペラ座の定期会員、つまり座席を年間単位で購入しており、その付帯サービスとして、舞台裏などへの出入りも自由であった。だからドガはよくオペラ座に通いそのバックヤードの様子を多く絵に残した。この絵の中でコンサートが行われているのは、今のオペラ座ではなく、昔のパリオペラ座。
この絵の独特なところは、普通観客がオペラ座に見に来るもの、つまりステージ上のバレーのパフォーマンスが完全に背景に追いやられていることだ。絵の中心を占めるのはオーケストラだ。オペラ座では普通オーケストラは観客の耳に達するだけのものであり、眼にしてもらうものではない。オーケストラ団員の幾人かはドガの知り合いだったし、そのうちの更に何人かは友人だった。バスーン奏者もその1人で、いつもならオーケストラの後ろにいる彼を前面に置き直している。
オーケストラピットへのフォーカスをより明らかにするためにドガは描き終えた両側面と上部に更に手を加えた。ステージのバレリーナ達の頭部は、まるで偶然のようにた絶ち切られているが、これは当時の芸術家達にとってなじみ深い表現形式になりつつあった写真のフレーミングを思わせる。ここでドガは、眼が事物を近くする方法について学んだ事を、作品の上で実践している。
彼は、真に迫った絵画表現を探し求めていたが、そのために時には視野を意図的にゆがめるといった方法もとった。当時の人々にとっては、実に新しい実験的な態度だったといえる。
![Degas-_La_classe_de_danse_1874[1].jpg](_src/sc4455/Degas-_La_classe_de_danse_18745B15D.jpg) ○ドガ「バレエの授業」。これは日本に来たときに見たことがある(横浜美術館特別展)。
○ドガ「バレエの授業」。これは日本に来たときに見たことがある(横浜美術館特別展)。
オペラ座のダンサー達の練習風景を描いた連作の一つ。ドガはこの連作を1842年頃に始めた。この絵の力強さは、当時美術史上類のない主題の選び方とその扱い方の両方において、徹底した写実性と個性が認められるところにある。
まず、ドガは、バレリーナの舞台裏の実生活という、普通、観客が見ることが出来ない世界を描いている。更に、レッスン場を横から見た遠近法と画家の目の高さの視点を用いることで、この絵を見る人たちに、実際にバレーのレッスンを覗いているような印象を与える。
しかし実際には、この絵は踊り子一人一人をパズルのように当てはめて制作したものだ。この絵を完璧に写実的に仕上げるために、ドガは、バレリーナ達に自宅アトリエでポーズをとらせた。彼は、芸術における写実性は常に現実の再構成であり、自分の作品においては、多くのスケッチを元に周到に準備を重ねた仕事の成果である、と考えていた。また、写実性を支えるそうした緻密な仕事によって、独創的画家は、模倣画家や写真家的画家と一線を画し、真に自らの芸術を極めることが出来るようになるのだと考えていた。
ドガがこれほどバレリーナの仕事に興味を持った理由の一つは、バレーダンサーが完璧な踊りを目指すあり方が、画家の仕事と同じように疲れを知らない研鑽の連続である、ということにあったのだろう。
さて、画面の空間は、床と天井の斜めの線で構成されている。こちらに背中を向けた2人のバレリーナが前面にいる。彼女たちは、ルプソアールとしての機能を持っている。つまり、彼女たちの姿が、絵を見るものの視線を絵の奥へ直接振り向け、バックステージで指導している教師の姿を発見させる。教師がバレリーナの一人を指導している間、その他のバレリーナ達はくつろいでいる。一人などは、ピアノの上に座って背中を搔いている。画面の下、左側の隅にある場違いな感じのする水の缶には、はっきりとした用途がある。これは、バレリーナが床で滑らないように床板を濡らすためのものだ。見るものの注意はまた、広い床にも向けられる。ここでは、華やかなバレーの世界の裏にあって、誰も知らない毎日のレッスンがおこなわれている。まさにドガでしか描けないせかいが、そこに広がっている。
ドガの目的は、バレーのステージの裏にある平凡な現実を描くことだったからだ。そして、毎夜舞台にかかるバレーのパフォーマンスは、それに見合った長い労働と準備に支えられているということを示すことだったからだ。一種のドキュメンタリーがこの絵を通じてええ浮かび上がってくる。
 ○シスレー「ポールマルリーの洪水」。(「洪水と小舟」)。6枚連作中2枚がここにある。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○シスレー「ポールマルリーの洪水」。(「洪水と小舟」)。6枚連作中2枚がここにある。 (この写真はオルセー美術館のページから)
1876年、セーヌ川はパリ下流のポールマルリーと言う場所で洪水を起こした。シスレーはこの事件を目撃し、6枚連作のヒントを得た。この6枚のうち2枚がこの美術館に収められている。
主題そのものを除けば、風景の中で最も興味深い点は、動きと命だと、シスレーは書き残している。輝くように美しい自然の情景が、絵の主題となっている大事件からすっかり主役の座を奪っている。浸水が進んでいる深刻な状況が現れているにもかかわらず、この景色には何故か安らぎが漂っている。見るものは、まず、洪水の被害のことも忘れて水面にキラキラと反映している光をじっと眺めることになる。ボートの上の人々の影がこの情景を更に詩情に満ちたものとし、夢の断片のような趣すらも与えている。前面に建っている建物の斜めのファサードが、構成の中心に眼を導く。この絵は、窓と木々の垂直なラインによって構成されている。空に浮かんだ小さな雲たちは動いているように見える。この絵の構成の土台は、空だ。水と空を描くタッチは繊細なのに比べ、建物を描く絵の具は分厚く重々しいものだ。この対照は自然と空気の絶えず変わり続ける様相を表現するための意図的なものと思われる。
シスレーはパリ居住のイギリス人家庭で生まれたイギリス人。しかしシスレーは生涯を通じて飽きることなくセーヌ川の岸辺を絵にし続けた。彼は印象派会派の原則に則って常に戸外で制作した人。生涯を通じて油彩画だけでも900点を越える作品を残したシスレーだが、風景画以外の作品はわずか20点にも満たないとも言う。だからこんなエピソードもある。ある時マティスが「典型的な印象派の画家は誰か?」と印象派の第一人者とも言える画家ピサロに尋ねると、彼は「シスレーだ」と答えたということだ。
 ○シスレー「雪のルーヴシエンヌ」。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○シスレー「雪のルーヴシエンヌ」。 (この写真はオルセー美術館のページから)
1872年(パリコンミューンを避けるために引っ越したという説がありそうだとすれば、1871年・・・この説の方が正しいように思う)にパリから数キロ離れたルーヴシエンヌに引っ越したシスレーは、この村を取り囲む田舎の風景をいくつも描いた。例えばマルリーの森やセーヌ川、さらにはこの絵で取り上げられている田舎道と村の風景など。
シスレーは日中のすぐに消えてしまう瞬間を捕らえ、流れる雲を観察し、空を飛びながら描いているようだ。すがすがしい空気が彼のキャンパスの上を流れ、木の葉はまだ揺れている。
確かにシスレーがこの作品を屋外で描いたとすれば、それは冬の冷たい空気を体感して伝えるためだったのだろう。モネなどと同様シスレーも雪というテーマを色の実験に使った。短い筆使いで様々なニュアンスの青やすみれ色により、白い雪をまるで彫刻するように描いていった。そして、距離を強調するために、小さな暗い唯一の人影を一番奥に配置している。
![Glyptoteket_Degas1[1].jpg](_src/sc4461/Glyptoteket_Degas15B15D.jpg) ○ドガ「彫刻 踊り子」。14才の少女のあまりにもリアルすぎる姿は当時不評だったそうだ。これも日本で見た(横浜美術館特別展)。
○ドガ「彫刻 踊り子」。14才の少女のあまりにもリアルすぎる姿は当時不評だったそうだ。これも日本で見た(横浜美術館特別展)。
この作品に日本で対面した時の強い印象は今でも忘れられない。オルセーでは硝子ケースに入っていたが、記憶では日本では遠巻きに硝子ケース無しに見たように思う。その衝撃は強く伝わってきた。
1881年の印象派展に出品されたこの作品を見て、憤った批評家達はこう叫んだ。これは剥製じゃないか、と。ドガの写実主義は極限にまで推し進められている。まず、少女の姿をほぼ実物大で復元したこと、それから、蝋の素材を使ったことによってだ。蝋を使うことによって、ドガはこの彫像に人間の髪の毛や本物のチュチュやサテンのリボン、バレーシューズなど実際の物品を加えることが出来た。
ブロンズの鋳型は後に作られた。しかしドガの写実主義はディティールにとどまらない。彼は激しいバレーの練習が原因で起こる身体のゆがみを見逃さなかった。少女の骨の関節などが、そう。その結果、14才の踊り子の姿は、あまりにも現実味を帯びていて、彫刻というよりもまるで人類学的な標本を見ているようだ。そして、その点がまさに当時の批評家や観客に不愉快な思いをさせた理由なのだ。ある新聞記者などこの少女を猿に比べた。
実際のモデルについて、NHKの番組で追求をしていた記憶がある。彼女は一時期経済的な理由で踊り子を目指したらしいが、やがてオペラ座のリストから消え去っている。そうした事情も、またこの作品にミステリアスさを加味させている。
![Auguste_Renoir_-_La_Balan%C3%A7oire[1].jpg](_src/sc4463/Auguste_Renoir_-_La_Balan25C325A7oire5B15D.jpg) ○ルノワール「ぶらんこ」。
○ルノワール「ぶらんこ」。
この作品は、次に言及する「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」とともに第3回印象派展に出品された。後ろ姿の男が、ブランコの上に立った若い女性に話しかけている。木にもたれかかったもう一人の男が二人の方をにこやかに眺めている。一方で小さな女の子は、ブランコの上の女性から目が離せないようだ。これは、眼差しが縦横に戯れている絵だ。その真ん中には、女性と女性に話していてこちらには背を向けている男性の間の距離が非常に意味深く配置されている。この絵を見るとき、誰でも考えることは一つだけ。彼は彼女を口説き落とすだろうか、二人の間の距離は縮まるだろうか、という疑問だけ。
音声ガイドの話すこうした物語が浮かぶのは十分に根拠のあるもののようだ。この絵は、セザンヌも強い関心を示した、ゾラの「愛の一頁」に影響されたものらしい。別掲の鑑賞本にそのことが書かれている。『「ぶらんこ」は1878年に刊行されたゾラの「愛の一頁」に着想を与えたと思われる。ゾラは「たったまま小さな板の上に乗り、腕を開して縄を掴む、…彼女は薄紫色の飾りリボンのついたグレーのドレスを着ていた。…この日、青白い空の下、太陽が金色の塵を振りまいていた。それは葉の落ちた枝の間からゆっくりとこぼれる光の雨だった」と書いている。』
ルノワールの印象主義の特徴は、楽しみや喜びを感じた瞬間をそのまま伝えるところにある。恋愛感情は、彼の作品の大きな主題だ。ルノワールのブランコには、18世紀の画家、フラゴナールの同名の絵に通じるところがある。フラゴナールの絵は、常に恋愛沙汰に題材をとっていたが、ルノワールは元々陶器の絵付けの修行から絵画に入ったため、陶器の世界に名高い18世紀絵画のモチーフを良く知っていた。しかし、勿論、ルノワールが描く恋模様は、18世紀貴族社会の浮気沙汰とは大きく違うのだが、ルノワールの絵も、その他の印象派の作品と同じく、戸外のオブジェを非常に注意して眺めた結果生まれたものだ。古典主義絵画では、戸外の事物の影は、常に灰色で描かれていたものだが、ルノワールの絵では、多彩な色で描かれている。この絵のためにポーズを撮ったのは、ルノワールの弟エドモン、画家グーヌート、そしてモンマルトルの女性ジャンヌだった。彼らの肖像は、ルノワールのもう一つの作品「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」にも見られる。
![Pierre-Auguste_Renoir%2C_Le_Moulin_de_la_Galette[1].jpg](_src/sc4465/Pierre-Auguste_Renoir252C_Le_Moulin_de_la_Galette5B15D.jpg) ○ルノワール「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」。あまりにも有名な絵だ。
○ルノワール「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」。あまりにも有名な絵だ。
モンマルトルは、1860年にパリ市に併合されるまで、独立した村だった。その後も長くモンマルトルには、まだ牛のいる牧場や動いている風車が残っていた。パリ市の一部でありながら、半分、村の性格も残していた。休息を求めるパリの人々は、モンマルトルの野外レストランやダンスホールに詰めかけた。画家達もまたモンマルトルの労働者の世界に都会を離れた安息の地を見つけたのだった。
ルノワールの作品の多くがそうだが、この絵でも彼の目的は、楽しみや幸せな感情を描き、視覚的な経験をそのまま絵の中に写し込むことにあった。この絵の舞台は、モンマルトルで一番有名だったダンスホールの一つ「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」だ。まるでスナップ写真のような感じの絵だ。しかし、この印象深い絵は、実はきわめて緻密に構成されている。この絵のためにポーズをとっているのは、ルノワールの友人達とモンマルトルの知人達だった。その中には、ジャンヌとその娘エステルがいた。ベンチにいるのがジャンヌ、彼女に身をかがめているのがエステル。
印象派絵画の原則に従ってルノワールはいつも戸外で制作した。実際問題、これを友人と二人で毎日自宅からムーランまで運んで描いたと言うことだ。さてそうした努力の結果も手伝って、この絵は、日中の自然光の下で見た情景が描かれている。当時まだ新しかった電灯の光は庭園でのダンスの目新しい飾りだった。自然光と電灯の光が混ざり合った様子は、きわめて写実的に描かれている。特に、人々の頭上の木々の茂みの間から差し込む太陽の光が斑になっているところなど、秀逸だ。しかし、当時の批評家が嫌ったのは、まさにこうした光をにじませて人物すらも空気に溶け込んでしまったかのように見せる絵の具の効果だった。
この絵は、画壇から非常に冷たく迎えられた。
![Edgar_Germain_Hilaire_Degas_084[1].jpg](_src/sc4467/Edgar_Germain_Hilaire_Degas_0845B15D.jpg) ○ドガ「アイロンがけをする女性達」。あくびをする女性を描くことで疲れている女性を描いた。 この引用したwikipediaの画像は少し荒い。それから不必要に彩度をいじっている。本当はもっとパステル調の絵である。オルセーのページの方が見た目もっと近い。
○ドガ「アイロンがけをする女性達」。あくびをする女性を描くことで疲れている女性を描いた。 この引用したwikipediaの画像は少し荒い。それから不必要に彩度をいじっている。本当はもっとパステル調の絵である。オルセーのページの方が見た目もっと近い。
19世紀には都市部の人口はコンスタントに増大していた。そして、ドガがこの絵を描いた頃、都市の労働者階級は殆どが工場で雇われていた。しかし、勿論、数千人の女性達は、家事を手伝う不安定な日雇い仕事を求めていた。例えば、洗濯、裁縫、アイロンがけなどだ。こうした状況に問題意識を持ったアーチストたちは、彼女たちの生活や労働状態を表現した。
エミール・ゾラは、1877年に出版した小説「居酒屋」の中で、一人の自分の店を持つ洗濯女、ジェルベーズの生活がアルコールによって次第に破壊されていく様子を描いた。ドガもまた、この問題に関心があった。そして1869年にこの「アイロンがけをする女性達」の肖像を描いた。2人の女性のうち一人がアイロンをかけ、もう一人があくびをするこの絵は、同様の4枚の絵のうちの1枚だ。ドガは、非常に良く観察されたあくびをする女性のジェスチャーによって彼女たちの疲労感をまっすぐに伝えている。彼女が、ワインのボトルを片手に持っていることで、ドガは、飲酒が彼女の毎日の習慣となっていることを示している。これは、ゾラの問題意識と同様のものだ。もう一人の女性は、自分の体重をかけてアイロンを押しつけており、こうした女性達がどれだけ力仕事をしなければならないか示されている。この絵には、はっきりした社会性があるが、ドガはここで善悪の判断をすることを避け、ただ、毎日の生活の中の一場面を観察した結果を表現するにとどめている。
またこの絵画を通じてわかることは、画家が対象とするものが、庶民やその庶民が出てくる情景にこの時代広がったことをも占めしている。こうしたことは、大きく価値観がこの時代に変わってきたことが暗示される。都市労働者の何気ない一コマに、そこに労働する人々に芸術的な美を見出したドガは画家の一人であった。
![Rodin_The_bronze_age[1].jpg](_src/sc4469/Rodin_The_bronze_age5B15D.jpg) ○ロダン「青銅時代」。リアルすぎて、モデルをなぞったのではないかと疑われ、それが却ってこの作品で名をあげた。彫刻家ロダンのターニングポイントとなった、記念碑的作品。
○ロダン「青銅時代」。リアルすぎて、モデルをなぞったのではないかと疑われ、それが却ってこの作品で名をあげた。彫刻家ロダンのターニングポイントとなった、記念碑的作品。
ロダンが初めて世に認められた作品が、1877年ベルギーで発表されたこの「青銅時代」。ロダンは既に37才になっていた。ロダンは、この実物大の男性裸体習作によって自分の完璧なモデリングの力を証明しようとした。しかし、人物像の実物そっくりの肉体に驚いたベルギーの批評家は、ロダンが、モデルから直接型を取ったに違いないと疑った。その後、ロダンは、パリのサロンでも同じ疑いをかけられた。仕方なく彼はこの作品が自分の手でモデリングされたものだと証明する友人の証言を集め、モデルとなった若いベルギー人の兵隊オーギュスト・ネイトの写真を含めた反証の書類を構成した。また、2年後に人間よりもかなり大き目のサイズの彫刻を新たに作って、反証とした。
1880年、パリの美術学校の校長がやっと買い取ることにしたが、それまでには高名な彫刻家がロダンを支持する必要があった。結果的に、デビューにおいてこのような疑いにさらされ、話題を集めたことは、ロダンにとって名声を高めるきっかけになった。その後、彼の元には公式の注文が相次いだ。そのうちの一つに、パリ、アールデコ博物館の正面玄関がある。この玄関は、後の地獄の門として完成した。(アールデコ博物館はその後建設が中止されたが制作を彼は続け、皮肉にもその跡地には今日のオルセー美術館が建っている。)
青銅時代を制作したとき、ロダンの心に何か特別な次第の意識があったようには思われない。おそらくこれは単純に男性裸体の習作だったのだろう。ロダンは最初、この彫像に、「歩く男」や「打ち負かされた男」という様々な題を付けた。最終的に青銅時代が選ばれたのだが、これはローマの詩人、オビディウスによる神話的な人類史の四区分の一つから借りてきた題だ。オビディウスは、人間文明は、黄金時代、銀の時代、青銅時代、そして鉄の時代へと進んできたと見なしていた。ロダンは、神話的主題を借りてくることで、サロンにややおもねったといえる。何故なら、サロンに出品するためには何らかの主題がなければならなかったからだ。ロダンは、単なる裸体習作にいかめしい題名を付けて、まるで寓話的作品であるかのように思わせたわけだ。
 ○ピサロ「羊飼いの少女」。第7回の印象派展に出品された。ピサロは印象派の長老だ。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○ピサロ「羊飼いの少女」。第7回の印象派展に出品された。ピサロは印象派の長老だ。 (この写真はオルセー美術館のページから)
印象派とよばれる多くの画家達よりかなり年上のピサロは、「印象派の長老」とか「印象派の父」と呼ばれることが多い。実際、彼はモネやルノワールとは10才の年の開きがあった。また73歳まで生きた彼は、この時代からしてみれば比較的長命だったと言える。
また、ピサロの画家としての経歴も、ほかの画家達とは異なっていた。彼の師はカミーユ・コローだった。クールベがその作品で写実主義の到来を告げたときにはまだ20才だった。この絵でも彼の高い写実性は明らかだ。それは普通の人々の日常生活と仕事へのたゆまざる関心に現れている。これは、彼と並んで後に印象派と呼ばれた画家達よりも遙かにそうしたことへの関心が高い。
この「羊飼いの少女」の絵にも、繊細な自然描写以外にピサロの社会的関心が伺える。ピサロは、何気なく木の枝で遊んでいるように見える少女を通して彼女の重労働に耐えなければならない一生を見通しているようだ。あるいはそうしたことを意図して描いているように見える。また、その他の印象派の絵と違って、この絵は写生を元に描かれたものでは無く、注意深く構成されたように見えるのが特徴といえる。
 ○メアリー・カサット「庭で縫い物をする若い女」。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○メアリー・カサット「庭で縫い物をする若い女」。 (この写真はオルセー美術館のページから)
メアリー・カサットは、生まれはアメリカだが、生涯の殆どをフランスで過ごした。ベルト・モリゾとともに、印象派女性を代表する人。1874年、彼女はエドガー・ドガの作品に出会い、彼と親交を結ぶようになる。女性嫌いのドガだったが、彼女のデッサン力に驚愕し、彼女に多大なる影響を与えた。彼女に印象派の出典を薦めたのは彼だった。
彼女の作品には明るい色使いなど印象派との類似点があり、1879年に行われた第4回の印象派展以降、何度か出品している。確かに彼女の光に対する興味と扱い方は、印象派の画家達に近いものだ。しかし、複雑な遠近法を元にした構図の取り方は、ポスト印象派に近いものだ。
この作品では、女性の背後の斜めの道が奥行きを生み出しており、数年後にナビ派に影響を与える日本の浮世絵を想起させる。また、女性のとっているポーズは彼女の着ているドレスを波打たせて装飾的な効果を高めており、これもまた日本的だ。1890年以降、彼女は日本風版画を何点か制作している。
また彼女はアメリカ人で有り、アメリカに印象派の絵を紹介した功労者でもある。印象派の絵をアメリカ人が購入するきっかけも作り、そうした資金は貧しい印象派の画家達の経済を大いに潤したとも言う。そうした点でも、忘れてはなら無い画家と言える。
 ○セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」。この山は以前実際に見てきた。セザンヌのアトリエにも行った。セザンヌはこの題材で80枚もの絵を描いたそうだ。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」。この山は以前実際に見てきた。セザンヌのアトリエにも行った。セザンヌはこの題材で80枚もの絵を描いたそうだ。 (この写真はオルセー美術館のページから)
サント=ヴィクトワール山は、南フランス、エクスアンプロヴァンスの東、数キロ先にある丘だ。エクスアンプロヴァンスはセザンヌの故郷だ。セザンヌはその生涯の一時期、印象派の画家達と共にその作品を展示していたことがあった。この時期には、彼も戸外で主題に直接あたって制作した。そのためその頃の生活の中で常に見ていたサント=ヴィクトワール山の姿がセザンヌの作品に頻繁に現れるようになった。また、1870年以降のセザンヌは、サント=ヴィクトワール山だけを研究し、この山を描いた80枚もの絵を残した。長く描くうち、彼は次第に装飾的なリテールをはぎ取るようになり、純粋に丘陵そのものの形を追求するようになった。セザンヌの最後の作品は、殆ど抽象絵画に近いものだが、その中でもサント=ヴィクトワール山の存在は圧倒的なものだ。
この風景画もその構成は完全に山が支配している。風景全体が、徐々に高くなる山の稜線に合わせて上昇しているように見える。絵の下部分の左側には壁が見える。この壁はテラス上にある貯水槽の一部だ。このことから、セザンヌがどの位置にイーゼルを置いて写生していたかが分かる。セザンヌは、サント=ヴィクトワール山を写生するため、少なくとも10カ所以上の場所をピックアップしていた。どの絵の山も似たような稜線を見せるのは、常に西側から写生しているからだ。右手には、陸橋があり、アルク川を横切っているのが見えるが、この視野もセザンヌが水浴する人たちを描いた多くの絵に共通している。
彼は何度も同じ題材を取り上げる傾向があるが、これは彼にとっては題材は大事なことではなかった。彼が興味を持っていたのは、絵画の可能性を限界まで試すことだった。そして、彼は一枚一枚の絵を、彼の妥協ない実験を更に先へ進めるチャンスとして描いていた。
こうした姿勢は、「近代絵画の父」と呼ばれるに至ったわけだが、そのことはまた別項で触れたい。
![Paul_C%C3%A9zanne_-_Les_Joueurs_de_cartes[1].jpg](_src/sc4477/Paul_C25C325A9zanne_-_Les_Joueurs_de_cartes5B15D.jpg) ○セザンヌ「カード遊びをする二人の男たち」。
○セザンヌ「カード遊びをする二人の男たち」。
セザンヌはカード遊びする人たちをテーマに5枚の絵を描いているが、それぞれ違う描き方を選択している。この作品で彼が選んだのは、人物が2人だけのシンプルな構図だ。彼は、人物を、取り囲む周囲の風景に溶け込ませようとしているようだ。当時ゴーギャンは、作品の題材に優先順位を付けず、色面を平坦にするサンテティズムという手法に取り組んでいたが、この作品でセザンヌが目指していることもこれに近いようだ。
カード遊びに熱中している2人の男には、全く動きがない。この動きのなさと絵の大部分を占める黄土色が彼らに無機質な人間と物の中間のような印象を与えている。そのためこの絵を見ていると風俗画というより静物画を見ているような気がする。比較すると、左側の人物はより図式的に描かれている。シンプルなラインを使って肉体の膨らみは最少限に押さえているので、例えば腕などは、L字型のパイプのようだ。
この連作の更に興味深い点は、最初の作品では観戦者など5人の人物が登場していたが、2枚目では4人に減り、とうとうこの作品では二人だけになってしまった。使われている色の数も同じように少なくなっていったという。余分なものを全てはぎ取り、ゲームがまさに始まろうとしているその一瞬の緊張した情景を描いている(何故なら机上に未だカードは一枚もないから)。迫ってくる静寂感は、この二人の男(農業労働者だと言う話だ)の孤独感となって見るものに伝わってくる。
 ○モネ「睡蓮」。連作の中の1枚。 (この写真はグーグルプロジェクトのぺーじから)
○モネ「睡蓮」。連作の中の1枚。 (この写真はグーグルプロジェクトのぺーじから)
連作の中の1枚。1880年代後半、クロード・モネの絵には、うなぎ登りに高い値が付くようになった。裕福になったモネは、1890年、数年前から住んでいたジベルニーの家を買い取った。ジベルニーに落ち着いたモネは、彼が水の庭園と呼んでいた庭の造園計画を実現に写すことが出来た。この庭の最大の見所は、池だ。モネは、この池で睡蓮を育てていた。また、彼は、睡蓮のことをその学名であり、また最も詩的な呼び方であるドュンフェアという名で呼ぶことを好んだ。モネは晩年になって「私が造った一番美しい傑作は、私の庭だ」と言った。
1910年、この人工楽園でモネは装飾絵画の大作に取りかかった。睡蓮の池は、彼が美的探求に没頭する戸外の実験室となった。彼は池の上に揺らめく睡蓮の花を飽くことなく観察し、絵にした。睡蓮のモチーフは、モネの絵の具の中にすっかり溶け込んでしまったようだ。彼は睡蓮の絵を巨大な連作にしようと考えた。彼は、絵を見る者に睡蓮の池のまっただ中にいる気持ちを与えるよう構想した。1918年、第一次大戦が終結を向かえた日、モネは連作の8枚をフランス政府に寄贈した。政府はこの作品をトゥールリー宮殿にあったオランジュリー美術館の楕円の続き展示場に設置した。オランジュリーの展示室は、楕円の部屋が二つ重なって出来ている。この場所は、モネの果てしない空間という考えに合致し、また、一切境界というものを描き込まれていない絵という物を展示するのに最適な場所だった。
「睡蓮」では、いくつかの睡蓮の花がクローズアップされ、水面に反映している様子をモネの繊細で生き生きとした筆の動きがキラキラと描いている。キャンバスには、裸のまま残されている場所もあるが、これは、この絵がまだ素描の段階にあったかも知れない可能性を語っている。水に映った影は、おそらく木々だろう。しかし、岸辺が描かれていないために、この絵を見る者は必ずたゆたう水の中にすっぽり浸かっているような気持ちになる。
 ○セザンヌ「コーヒーポットを持つ女」。背景の描き方などからピカソ達はセザンヌがキュービズム運動の真の父であると捕らえていた。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○セザンヌ「コーヒーポットを持つ女」。背景の描き方などからピカソ達はセザンヌがキュービズム運動の真の父であると捕らえていた。 (この写真はオルセー美術館のページから)
この絵は、セザンヌが行っていたボリュームとフォルムの単純化をまざまざと見せてくれる例。モデルの女性は、こわばった殆ど木の人形のような姿をしている。その姿が、正面から左右対称に捕らえられている。ピラミッド型の彼女のシルエットは、絵の下半分にどっしりと腰を下ろしている。画面のピラミッド型構成は、座った農夫像と共通する物だ。農夫像もまた、近年オルセー美術館の収蔵品になった。どちらの絵においてもセザンヌはモデルの手を強調している。彼らが手に職を持った人々であることを意識させるためかも知れない。このモデルの女性が誰なのかは知られていない。ただ、どこかの家政婦か召使いであったろうと想像される。いずれにせよ、セザンヌは彼女のアイデンテティーには関心がなかった。彼は自分がどのように彼女を表現するかにしか関心がなかった。
後にパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックは、幾何学的な形の探求に基礎を置いていた最初のキュービズムの絵を描いた時に、セザンヌこそキュービズム運動の真の父であると宣言した。彼らはセザンヌの静物画を研究していた。セザンヌはこの絵の、奥が持ち上がっているように見えるテーブルのように、全く非現実的な遠近法を使った静物画を描いた。
セザンヌの、特に後半生の静物画を見ると、ものを多面的に見る視点を感じることが出来るが、この絵を見ると、確かにピカソの曲がった顔の女性像などの作品の源流を見ることができる。ピカソらの言葉は寄り真実みを持って迫ってくる。
 ○ルノワール「浴女たち」。晩年の作品。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○ルノワール「浴女たち」。晩年の作品。 (この写真はオルセー美術館のページから)
晩年のルノワールは、過去の巨匠達と張り合うような最後の絵画的探求に取りかかった。ルノワールの作品は、印象派の歴史を大きく左右し、印象派の到来と発展は西洋絵画にとって前例のない極端な転換をもたらした。
人生最後の時期に入って、絵画の伝統的な主題や手法へと立ち戻ろうと考えた。印象派の、ものの輪郭や美しさを忘れてしまったことに対する懐疑から、古典への回帰を模索したとされている。彼の最後の作品の一つであるこの絵は、楽園のような舞台で水浴している女性達を描いている。これは明らかにティッチアーノやルーベンスの模倣だ。2人の肉感的な女性はこの一時の甘くけだるい時間に、ただうっとりと身をゆだねているようだ。彼女たちの背後では、やや遠い場所で3人の女性が水浴をしている。地中海の豊穣な自然の中で、女性の肉体の表現は、官能性の極みに達している。ルノワールは、カーニシュルメールの自宅庭園で、モデルを前にこの絵を制作した。ルノワール本来が持つ甘美な世界を描ききった作品と言えるだろう。
彼はこう言っている。「何と言っても女性の裸体で一番好きなのは、肌だ。少女のピンクの肌は循環の良さを示している。私が一番愛しているのは、穏やかさだ。」・・・晩年のルノワールは、それまでにもまして、生きる喜びを絵の中に注ぎ込んだ。しかし、その頃、老いた画家の手はリューマチで硬直し、筆を持つことさえ困難になっていた。
 ○アンリ・ルソー「女性の肖像」。 (この写真はオルセー美術館のページから)
○アンリ・ルソー「女性の肖像」。 (この写真はオルセー美術館のページから)
アンリ・ルソーは税関吏ルソーという面白い渾名で知られている。パリ市の税関で働いていたからだ。彼は、完全に独学の芸術家であり、絵についても初歩の規則をかろうじて知っていただけだった。彼が個人的に開発した特殊な様式は、当時の批評家達からしばしば嘲笑されたものだが、同時にナイーブアートという概念も生み出した。
この肖像は全身像だ。空間的なエレメントを沢山並べることで作られている絵なのに、一切の奥行きを感じさせない。女性のなだらかな肩と膨らんだ袖のラインに沿って木の枝が描き込まれている。こうした人物の周りの二次元の景色は、背景というより単なる装飾のように見える。画家は、モデルに動きのある姿勢をとらせているが、モデルはポーズをとったまま凍り付いてしまったようだ。彼女の顔もあまりにも無表情だ。彼女の足下で毛玉にじゃれついている子猫だけが唯一生きている物のように見える。
ルソーは気象条件を非常に精密に描いた作家である。それ故、彼の自然描写は豊かで秀逸だ。彼の作品の中で最も賞賛されているのは、「熱帯のジャングル」の絵だが、その絢爛たる夢の植物のモチーフは、ルソー絵画のトレードマークとなったほどだ。その後、ルソーの作品のナイーブさは、前衛的な芸術家の関心を惹くところとなる。ピカソもこの肖像に似た別の肖像を購入している。伝統的絵画の約束事から解放されて自由になろうとしていたピカソにとって、プリミティブなルソーの絵は、これまでに学んだ規則を放棄し、もう一度子供の絵のような新鮮さを取り戻すための大きな足がかりに見えた。ピカソは、バトーラボアール、洗濯船にあったアトリエでルソーに敬意を表す宴会を開いた。招かれてやってきたルソーは、このときピカソにこう言ったと伝えられている。「我々は今の時代に生きる最も偉大な2人の画家だ。君はエジプト様式で、私はモダンアートの様式で。」
印象派の画家達や批評家からは嘲笑され続けた彼ではあるが、独創的な世界を自ら編み出した芸術家は、こうして次の世代の橋渡しの役割をも果たし、その美術史的位置を見事に獲得したのだ。
 ○モネ「外光における人物の試み」、別名「左向きの日傘の女」。この絵は印象に残っているのだが、解説はなかったようで残念だ。(この写真はオルセー美術館のページから)
○モネ「外光における人物の試み」、別名「左向きの日傘の女」。この絵は印象に残っているのだが、解説はなかったようで残念だ。(この写真はオルセー美術館のページから)
購入した解説本には、以下のようにある。
『~画壇にデビューした当時、風景画の中に等身大の人物像を取り込もうとしたモネ(「草上の昼食」、「庭の女たち」)は、その後この挑戦を諦めていたが、1885年以降それを再開したのである。彼にとって重要なのは、習作のように顔立ちがかろうじて確認できるようなスケッチで2番目の妻の娘シュザンヌ・オシュデの肖像画を描くことではなく、この数年後に制作される「積み藁」の連作に見ろれるように、一瞬のうちに捉えた空気と光を描くことであった。~ギュスターヴ・ジェフロワは説明している。「…ある時は、我々の前に赤い花々が咲き乱れる草原を出現させ、…またある時は、太陽の金色の輝きと雲の動きの中に、すらりとした、空中に漂うリズミカルな若い娘の姿を置いて見せる。彼は、移ろいやすい光が宇宙に及ほす影響を絶えず追い求める大地と空気の画家である。彼は、生まれてすぐに消え、二度と戻ってこない束の間の感動を与えてくれる。絶えず変化する肖像、風景の様相、我々が感じる喜びや絶望、神秘さや宿命の外観、つまり我々を取り巻くすべてのものを明らかにしてくれるのだ」。』
この娘は、当時のパトロンの娘を描いたとされるが、同趣旨のものは
解説本のタイトルに、「空気を描くこと」とあったが、画面一杯に感じる陽光の中に、そよ風になびく裾やスカーフの中に、確かに感じるさわやかな空気を見事に描いていると言える。
音声ガイドの順に沿って記録したが、勿論このほかの作品も多数あって、目にしている。とにかく名画と言われる作品が所狭しと並んでいた。印象派と言えばオルセーという評価通りの圧倒的物量であった。
5階の印象派ギャラリーに隣接する大時計裏のカフェ。ここだけは写真が撮れそうなので、一枚記念に。(前の項目に便宜上載せた)
その後、階段を伝って下に下りる。が、これがなかなかわかりにくい。
8-3-2 ゴッホ・ゴーギャン
オルセー美術館にとって、ゴッホは特別な画家のようだ。彼のために特別に部屋が設けられている。
![1280px-Starry_Night_Over_the_Rhone[1].jpg](_src/sc4498/1280px-Starry_Night_Over_the_Rhone5B15D.jpg) ○ゴッホ「星降る夜」。
○ゴッホ「星降る夜」。
アルルから弟のテオに宛てて書かれた手紙の中で、ゴッホは、描き終えたばかりの「星降る夜」について語っている。「空は青緑で、水はロイヤルブルー。地面は藤色だ。町は青と紫で、ガスランプは黄色。その赤と金の反射は、ブロンズの緑色の中に下りていく。空の緑色の辺りには、おおぐま座が緑とピンクで煌めいている。その控えめなほの明かりはガスランプの乱暴な金色とコントラストをなしている。前景には色の付いた恋人達の人物像が二つ。」
ゴッホは、少し前にアルルに向けてパリを発ったばかりだった。それは彼が、フランスの現代美術をもっとよく学ぼうと1886年にフランスに来てから2年後のことだ。印象派グループの最後の展覧会で、彼はスーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」を目にした。彼のいわゆる色彩分割テクニックは、印象派を受け継ぐ者と見なされていた。彼がパリにいる間、ピカソとシニャックはゴッホに色彩分割の手ほどきをした。「星降る夜」の断片化された筆使いは、こうした出会いの影響の名残がまだ見られる。ゴッホは、印象派から自由になりたくて、パリを離れ、南仏を目指した。彼は弟宛の手紙で、「パレットは南の光の中で、かなり豊かになった。」と述べている。数ヶ月後、彼はサンレミドプロヴァンスの精神病院に入院する。そこで彼は「星降る夜」をもう1枚描いた。今度は以前よりずっと苦しみながら。これはだんだんひどくなる彼の精神的な病を反映した物になった。
なお以下同様だが、特記しない限り、絵画画像の出展はWikipediaから。
 ○ゴッホ「真昼」。あるいは「真昼の休息」。(この写真はグーグルプロジェクトのページから)
○ゴッホ「真昼」。あるいは「真昼の休息」。(この写真はグーグルプロジェクトのページから)
ゴッホは、自ら望んで、サンレミドプロヴァンスの病院に入院したとき、創作意欲が非常に高まっていた。しかし、病院で隔離されていては、絵の題材を十分に見つけることは出来なかった。そこで、彼は、過去の偉大な画家達の作品の模写を始めた。1887年にパリの美術学校で見たドラクロワとミレーの作品だ。
弟への手紙の中で、「ミレーの7作品を模写した。」と言っている。
「真昼」。仕事の間の昼寝は、ミレーの絵の模写だ。しかし、ゴッホのものは左右逆になっている。それは彼がこれを左右反転した印刷の複製画を元に描いたからだと言われている。更にゴッホが、病院の自室に持っていた物は、モノクロ印刷の複製画だったため、彼はミレーの絵をもっとずっと鮮やかな色に変え、まぶしい真昼の太陽を表現した。
ゴッホは弟テオへの手紙の中でこう説明している。「我々画家は、いつも創作するように求められている。何でも全部自分でやれというわけだ。よろしい。しかし、音楽では事情が違う。人はベートーベンを演奏し、そのときに自分なりの解釈をそこに加えるのだ。私は、ドラクロワやミレーの印刷の複製画を画題として自分の前に置く。それから私は、即興でそれに色を付ける。勿論、完全に私流ではない。彼らの絵の記憶を探りながらだ。しかし、その記憶が正確ではないとしても、同じ感情に基づいた曖昧な色の一致、それが私独自の本案という物なのだ。」
 ○ゴッホ「アルルのゴッホの部屋」。(この写真はグーグルプロジェクトのページから)
○ゴッホ「アルルのゴッホの部屋」。(この写真はグーグルプロジェクトのページから)
1888年、ゴッホは、パリを去ってアルルに向かった。彼は明るい南フランスの陽光に引き付けられていた。弟に宛てた手紙で、ゴッホは自分の絵画についての考えを述べている。アルルで住み始めた家の寝室を描こうとしていた彼は、どれほどその絵に色が大事かをこのように語っている。「ここで大事なのは色だけだ。そして、オブジェは単純化することで、そこに大きな様式性が生まれ、一般的には、見る者を休ませてくれる。あるいは、眠らせてくれる。つまり、この絵は、見る者の想像力を刺激したいのではなく、脳を休ませてあげたいのだ。」
この絵がどれほどゴッホにとって重要であったかは、この手紙の翌年、絵に損傷が起こったときに、ゴッホが2枚の複製画を作ったことからも分かる。オルセー美術館に残る複製画は、その2枚のうち小さい方の物。ゴッホはこのバージョンの物をまず妹に送った。彼は手紙を添え、この絵について次のように説明している。「明るい色で単純な主題を描くのは、全く簡単なことではない。しかし、グレー、白、黒や茶色といった色を使わなくても、オブジェを単純化して描くことが出来るのだということを示すことは役に立つかも知れないと思っている。」
日本で展覧会があった時に、その再現した部屋も見た。かなり小さな部屋だったと記憶している。
![851px-Self-Portrait_%28Van_Gogh_September_1889%29[1].jpg](_src/sc4504/851px-Self-Portrait_2528Van_Gogh_September_188925295B15D.jpg) ○ゴッホ「自画像」。
○ゴッホ「自画像」。
晩年のゴッホは、精神不安定のために、保護施設に入院していた。自殺の数ヶ月前、彼はシンプルであることの大事さを語る手紙を残している。「しかし、現代社会では、シンプルさという理想を掲げただけで、生きにくくなってしまう。私自身、今までずうっと秩序がない場所で苦しい思いをしてきた。結局、今ではシンプルさがどういうものか、秩序がどういうものか、そんなことすら分からなくなったんだ。」
画家自身による自画像は、単なる肖像というよりも内声の行為であり、彼自身による試作といえる。画家は、自分の姿を鏡に写して、そこに見える物だけを客観的に描いて自画像とすることも出来るし、あるいは反対に、自分の姿を理想化することも出来る。どちらのやり方でも、いつも彼について多くのことが分かる。ゴッホはルーブル美術館で、過去の巨匠達の自画像展を見た帰りに、このように書き残している。「僕が探しているのは、写真よりももっと深く、その人に似ている肖像だ。」しかし、ゴッホには自画像を制作するもっと経済的という現実的な理由があった。彼は1888年の手紙で、弟にこう言っている。「モデルがいないから、鏡に映った自分の映像だけで仕事が出来るように、十分大きな鏡を探して買ってきた。もし、僕が、自分自身の顔の色をきちんと描くことが出来なければ、良き魂を持った他のいかなる男も女も、僕にはその顔が描けないということになる。」 貧乏な画家達は同じようなことを皆していた。
ゴッホは、40枚以上の自画像を残した。これらの絵は、上記事情を反映して、彼の身体的及び、精神的な状態について教えてくれる貴重な資料となっている。また、ゴッホ自身、自画像をそのような意図で利用していたと思われる証拠もある。一年後の1889年、彼はまたしても弟への手紙でこう言っている。「おまえにも分かるだろうが、今、僕が書き終わったばかりの光を背後に加えた自画像を、僕がパリで作った自画像の脇に置くと、今の僕の顔は、ずっと健康そうに見える。本当に、すごく良くなって見えるんだ。もしかしたら、自画像の方が、手紙よりずっと良く今の僕を伝えてくれるかも知れないと思う。」
この部屋には自画像が2枚あったように思う。
![477px-L%27%C3%A9glise_d%27Auvers-sur-Oise[1].jpg](_src/sc4506/477px-L252725C325A9glise_d2527Auvers-sur-Oise5B15D.jpg) ○ゴッホ「オーヴェールの教会」。
○ゴッホ「オーヴェールの教会」。
写真にあるのは、普通のゴシック教会だ。ゴッホはこの教会を写実的に描こうとはしなかった。彼は教会の姿を自分の幻影によって変形し、それを絵にした。彼の震えるような筆使いは、建物と景色に生命を吹き込んでいる。大地すらも隆起して境界を讃えているようだ。ゴッホにとって絵画とは、現実を忠実に記録するものでは無く、ある感情を伝える物だった。
ゴッホはこの頃、益々激しくなる精神疾患の症状に悩んでいた。彼の絵画への願いは、こうした精神疾患から生まれたものだろう。ゴッホは、1886年、初めてパリにやってきた頃は、まだ印象派の影響から脱していなかった。印象派の技術をしばらく踏襲していたゴッホだが、すぐにそれは無くなり、非常に個人的な独自の様式が現れた。ゴッホの個人的な様式は、ゴーギャンやベルナール、また、セルジエといった画家の実験的なアイディアとよく合致していた。彼らは平板な塗りつぶしの部分と黒い輪郭線でオブジェを表現することで、主観的な表現の限界を広げようとしていた。ゴッホの鮮やかな色使いと現実を新たに形象化する方法は、マチスが率いていたフォービズムと表現主義など、20世紀初頭の前衛絵画に大きな影響を与えた。表現主義運動においては、画家は五感が感じたことをそのまま絵にすることで、絵画を個人的感性の表現とした。
解説本には画家自身の言葉が引用されている。なお、この文章中の「ヌエネン」というのは、ゴッホの育った村を指す。
『彼は1890年6月5日に妹ウィレミーナに送った手紙に、「これは、村の教会を描いたとても大きな絵だ。純粋なコバルト色の、混じりけのない濃い青色の空を背景に、建物は紫色がかっている。ステンドグラスの窓は群青色に見え、屋根は紫色で一部オレンジがかっており、前景には花の咲き乱れた草木とバラ色に輝く砂を置いた。ヌエネンで古い塔や墓地を描いたいくつかの習作とほぼ同じだが、おそらく色使いは今のほうが生き生きとしてすばらしいものになっているはずだ」と書いている。ヴァン・ゴッホが用いるタッチや色調はミレーのものとは似ても似つかぬものだったが、ヴァン・ゴッホはつねにミレーの作品に思いを巡らし、そこに『天上の何らかの証』を見出そうとした。』
 ○ゴーギャン「白い馬」。(この写真はオルセー美術館のページから)
○ゴーギャン「白い馬」。(この写真はオルセー美術館のページから)
ゴーギャンはこの絵を2回目のハイチ滞在中に描いた。しかし、見て分かるように、この絵の馬はそれほど白くない。馬の身体の上で揺れる光を表すために、ゴーギャンは非常に薄い緑の陰影を使っている。
この絵を依頼したのは、タヒチの薬剤師だが、彼は、馬が緑色すぎるという理由で、受け取りを拒否したことは有名な話だ。遡ること10年、ホンタベンで代表作「説教の後の幻影」をえがいたゴーギャンは、その絵の中の地面に赤を使うことによって、何の制限もなく自由に色を使う権利があるのだと既に主張していた。色の問題はともかくも、娘の死のショックから立ち直り切れていない精神がそう描かせたのだろうか。
彼がタヒチで探し求めていたのは、まだ文明に犯される前の進化の初期段階にある人々の人間性を表すものだった。しかし、彼の探検の旅は幻想に終わる。何故ならこの島は、遙か以前に西洋人によって植民地化されていたからだ。だから、この絵に描かれているのは、彼が見た現実と心の中に描いていた理想を混ぜ合わせたものなのだ。牧歌的な風景の中で、人間と動物たちが調和の中で生活している。この楽園では、騎士たちは裸馬に乗っている。エキゾチックな植物に囲まれた水の中で野生の馬は楽しそうに鼻を鳴らしているようだ。しかし、タヒチの人々にとって、白は、死とつながりを持つものだったため、批評家によっては、この馬を現世から次の世界へつながる道を象徴するものだとしている者もいる。
8-3-3 他
![868px-Dallas_Crow_Center_12_Bourdelle_Hercules_the_Archer[1].jpg](_src/sc4512/868px-Dallas_Crow_Center_12_Bourdelle_Hercules_the_Archer5B15D.jpg) ○ブールデル「弓を引くヘラクレス」。(画像の出展はWikipediaから。)
○ブールデル「弓を引くヘラクレス」。(画像の出展はWikipediaから。)
このヘラクレスの彫像を作ったとき、ブールデルは、50才になろうとしていた。その独自のスタイルは、成熟の頂点に達していた。この彫刻作品は、当時から批評家の絶賛を受けたが、現在でも、ブールデルの最も有名な作品だ。
主題は、ギリシャ神話の挿話、ヘラクレスの12の難行からとられた。6番目の難行としてヘラクレスに与えられた試練は、スティムパーリディスコから人を食べる怪鳥を退治することだった。ブールデルはここで、物語のクライマックスを描き出している。古代ギリシャの英雄ヘラクレスの張り詰めた力強い肉体が中心にある。ブールデルは、表現主義的スタイルをもっている。例えば、荒々しい周囲の雰囲気を強調するために、彼はこのようにゆがんだ形を岩に与えている。
ブールデルは、7年の間、ロダンの助手を務めた。ロダンは若い助手の彫刻家が到達しようと努力している事は何かを見抜いた。同時に2人が全く違う彫刻へのアプローチを持っていることもよくわかっていた。ブールデルはフォルムを単純にして、一つの動きに集中した構成を作った。古代ギリシャ彫刻を思わせるヘラクレスの顔は、様式化され、狩りの獲物に向かって張り詰めているという印象を作り出す。肉体もまた同じ印象をもたらす。一方ブールデルは、矢を見せない。見る者に想像させるのだ。ヘラクレスの力業に匹敵することをしたのは、彫刻のモデルとなった男性だ。彼は、ブールデルの前で、実に9分の間このポーズをとり続けた。この作品は、見事な構成例の一つでもある。ブールデルは、形と空間を完璧な形で配置し、身体と弓の動きを巧妙に対比させている。
8-3-4 見学を終えて
最後はかなりの急ぎ足になった。印象派の部屋もそうだが、ゴッホの部屋ももっとゆっくり見たかった。ゴーギャンの作品も他にも沢山あった。
急いで集合場所へ行くときに、上のブールデルの作品も見つけたのだ。
それでも時間的には、2時間もとったのだから、やはり1日では無理という所だ。
ルーブルも中途半端だし、あちこちの美術館巡りのための日程が必要らしい。それでも、今回ここへ来るのは日程に入っていなかったのだ。全く、添乗員さんの厚意に他ならない。有り難い。
帰りはまた地下鉄に乗って、ホテルへ戻った。ずっと雨が降り続いていたが、もう帰国であり、飛行機さえ順調に飛んでくれれば問題は無い。
8-4 ホテルにて
ホテル着(1240)
ホテルへ戻ると殆どの人がいた。
荷物を受け取って整理をしていると、メンバーの一人が、自動チェックインをしたかと聞いてきたので、「済ませた」と言うと不快そうな顔をした。「出来ない人はどうすればいいのよ。」と言うので、ロビーにあるパソコンを使えばいいと教えると、パソコンが使えないという。
やっかいなものだ。仕方ないのでnoriがやってあげることになった。
2人組の人と単独参加の人の3人分。時間ギリギリに取ることが出来た。
他の親子2人組は、既に自分たちでとっていたようだ。
また、一組の夫婦は延泊ということで、離団することになった。旦那は英語が、奥さんはフランス語が話せるので、うらやましい2人だった。
8-5 出発
ホテル発(1335)
バスとドライバーは昨日までとは代わり、空港の手伝いをしてくれる現地の人も来ていた。
さぁ帰国だ。
8-7 機内にて <エールフランス AF2318便 24BC>
バス乗車(1623)搭乗(1643)動く(1709)離陸(1720)軽食(1735)着陸(1815)
ここには使えるラウンジがないので、仕方なく58番ゲートへ行って、することもなく過ごしていた。ようやく、案内が始まると、バスでの移動だった。
機体は、エアバスA318。3-3の小さな飛行機だった。が、我が家は、何と最後部の2人席、しかも窓無し。まあ、乗っている時間が短いからいいか。
男女一人ずつの乗務員だったが、そのうちの一人は何と日本語が分かって話しかけてきたりした。以前日本にいたことがあるのだという。それなら日本便に乗務すればいいのにと思ったが、会社の都合とかもあるのだろう。
離陸すると軽食が配られた。軽食というよりスナックだ。しっかりワインも頂いた。
8-8 フランクフルトにて
チェックイン(1902)ラウンジ(1933~2010)手荷物検査場(2015)
継続してチケットが取れないので、ここでまたチケットカウンターへ行く。
添乗員さんが、自動チェックインをしていない人から手続きしてください、と言うので少し待ってからカウンターへ行った。簡単に済んだ。
自動チェックインで通路側が取れていなかった人たちもここで交換してもらえたようだ。やはり直前になると少し移動があるらしい。一組を除いて皆通路側が取れた。
それから全員揃って出国審査。これは簡単に済んだが、その後の添乗員さんの説明が長くて、ちょっとイライラした。旅慣れている人ばかりなのだから、出発ゲートを確認さえすればいいと思うのだが、買い物をするなら、とか、時間までどう過ごせばいいかとか、くどくどと話すのだ。まぁこの人の丁寧なやり方だと言えばその通りで、文句を言う筋合いではないのだけれど。というのも、我が家はここでラウンジを使いたかったものだから。
ようやく開放されて、ラウンジを探すと、それは手荷物検査場の前にあった。つまり、いつものようにラウンジで水を調達するということが不可能というわけだ。なんと言うことだ。
まあ、それでもゆっくり休めるのでいいかと、そちらへ向かった。
日本航空が、この空港に乗り入れて、丁度50年たつということで、案内の看板もあった。
時間が近づいたので、D51番ゲートへ向かう。何かお土産になるものは無いかと、免税店をウロウロしたのだが、結局何も買わなかった。
ゲートに入る前の手荷物検査場で、junは簡単に通過したが、noriが引っかかった。が、検査の結果問題は無い。帰ってからのニュースによると、問題は無くても何人かに一人は検査をすることになったようで、日本でも直にそうなるようだ。
8-9 機内にて <JL0408便 47BC>
搭乗(2045)動く(2109)離陸(2119)飲み物サービス(2155)食事(2245・・日本時間 +7時間 =0545)
座席は3人制の通路側。奥に日本人が座ったので、ホッとした。体臭の強い外国人の男性だとたまらない。
帰りもJALなので、気楽だ。やはり日本人乗務員がいるということと、日本の航空会社ということは大きな安心だ。
離陸してしばらくするとまずは、飲み物サービス。梅酒があったのでjunはそれにした。noriはウォッカ、というかトマトジュースで割ってブラッドメアリーごときものにする。
その後の食事は、やはり洋食と和食の2種類。メニューも日本語版でわかりやすい。メーンは洋食がビーフストロガノフ、和食が鶏丼。他に共通で、日本そば、サラダ、トンカツ、生ハム、トマト。飲み物は、junは今度はワイン、noriは日本酒。こうしたこと日本らしくて有り難い。

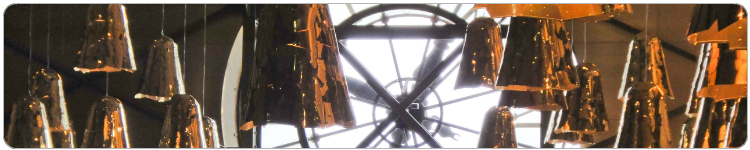
 9月10日
9月10日



































